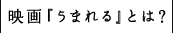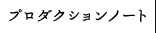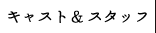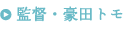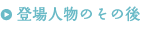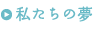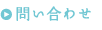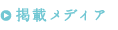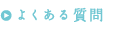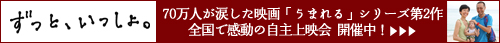-
<ナレーション> つるの剛士
1997年、「ウルトラマンダイナ」のアスカ隊員役を熱演し、一躍人気俳優に。2007年からは「クイズ!ヘキサゴンII」にレギュラー解答者として出演し、アイドルユニット羞恥心を結成。その後も数多くのテレビ、ラジオ番組に出演。2009年に発売したカバーアルバム「つるのうた」、「つるのおと」が大ヒット。
2010年オリジナル曲「夏のわすれものfeat.東京スカパラダイスオーケストラ」でデビュー。セカンドシングル「メダリスト」は「世界柔道大会2010」のテーマソングに。1男3女のパパ。2010年1月から2カ月間の育児休業を取得し、話題に。
<Message>
子どもたちの出産に立ち会い、命の大切さを実感し、育児休暇で家族の絆も深まりました。自分自身が感じてきた経験をもとに、ナレーションに挑戦させていただきました。全ての方に、命の大切さを感じてほしい映画です。ここにいる奇跡 出会えた奇跡 うまれる奇跡
すべての命のミラクルに改めて感謝。

-
<出演者>
伴まどか・真和
伴 真和(まさかず)(31歳)、まどか(31歳)夫婦は、結婚して約1年。妊娠6カ月のまどかは、初めてのお産が楽しみな反面、さまざまな不安も抱えている。
なかでも一番の心配は、自分が果たして良い親になれるのかどうかということ。
いつも笑顔の彼女だが、実は幼い頃に母親から虐待された辛い経験を持ち、彼女が中学生のときに離婚して家を出た母親とは絶縁状態だ。なぜ自分は母親に受け入れられなかったのか?
その答えを求めるようにして助産師の道を選んだのだが、いまだに自分と母親との関係を消化できていない。一方、真和は幼い頃から両親の不和を見てきたため、まどかと出会うまでは、結婚したいとも子供が欲しいとも全く思っていなかった。
そのせいか、父親になるという実感を持てず、妻のお腹の子は、あくまで「自分たちの副産物」でしかない。
戸惑い、悩みながらも、二人はどのようにして、母親、父親になっていくのか、そしてお腹の赤ちゃんの運命は...?

-
松本直子・哲・虎大
松本哲(あきら)(40歳)、直子(41歳)夫婦は、医療によって、18トリソミーという障害を持って産まれた虎大(とらひろ)――愛称・虎ちゃん(8カ月)と出会うことができた。
18トリソミーは染色体異常による重い障がいで、うまれること自体が難しく、うまれても90%の子どもが1年以内に亡くなる。
妊娠8カ月のときに18トリソミーの可能性を知った松本夫婦は、産むかどうかの選択を迫られたが、迷わず産むことを選んだ。そして、うまれた虎ちゃんは数ヶ月、NICUに入院した後、奇跡的に病院を退院し、家族との生活が始まった。
しかし、立つことも歩くことも話すことも出来ない我が子。。。
虎ちゃんは実際、自分で食事を摂ることができず、チューブで直接、栄養分を胃に送っている。松本夫婦は、どのように、いつ終わるかわからない虎ちゃんの命と向き合おうとしているのか?

-
関根麻紀・雅
関根雅(まさし)(32歳)、麻紀(31歳)夫婦の子どもは、出産予定日に突然、お腹の中で亡くなった。
娘に「椿」という名前をつけて見送った後は、深い悲しみの中で自分たちを責め続ける日々を過ごしていた。
そんな夫婦を救ったのは、「わたしがあなたを選びました」という本の著者である産婦人科医、鮫島浩二との出会いだった。自分たちを親として選んでくれたはずの子が、なぜ、うまれてくることができなかったのか? その問いに対して、鮫島医師は...?

-
東 陽子・徹
東(あずま)陽子(47歳)は、日本でも有数の不妊治療の病院、ミオ・ファティリティ・クリニックの管理部長。自身も30代のときに9年間、治療を受けた末に、子供のいない人生を受け入れた。最初の3~4年は「ワクワクしていた」と語る彼女。
しかし、やがて焦燥感などから精神的に不安定になり、そんな妻を夫の徹(50歳)は包みこもうとしていた。
クリニックには子供を堕ろす選択をした女性たちも訪れ、彼女を複雑に気持ちにさせる...


-
池川 明
池川クリニック院長(http://www1.seaple.icc.ne.jp/aikegawa/) 1954年東京生まれ。帝京大学医学部大学院卒。医学博士。上尾中央総合病院産婦人科部長を経て、1989年横浜市に池川クリニックを開設、現在に至る。2001年9月、全国保険医団体連合医療研究集会で「胎内記憶」について発表し新聞で紹介され、話題に。現在もお産を通して、豊かな人生を送ることをめざして診療を行なっている。著書に「おぼえているよ。ママのおなかにいたときのこと」(二見書房)、「ママのおなかをえらんできたよ。」(二見書房)、「胎内記憶」(角川SSCコミュニケーションズ)等多数。
〈Message〉
ドキュメンタリー映画『うまれる』は、私たちがなぜこの世に生まれてくるのか、その大きなテーマを考えるきっかけになるでしょう。私たちがそれぞれに貴重な存在である、ということを多くの人が知ることで、幸せを感じる人が多くなるはずです。世界に広めたい映画です。

-
鮫島浩二
さめじまボンディングクリニック院長(http://bonding-cl.jp/)
1981年、東京医科大学卒業。木野婦人科副院長、中山産婦人科クリニック副院長を経て、2006年、さめじまボンディングクリニックを開設。医学博士、日本アロマセラピー学会理事、国際ボンディング協会理事長。主な著書に、「わたしがあなたを選びました」(主婦の友社)、「その子を、ください。―特別区別養子縁組で絆をつむぐ医師、17年の記録」(アスペクト)、「命をつなぐ絆の話」(アスペクト)等多数。

-
大葉ナナコ
東京都出身。
有限会社バースセンス研究所代表取締役、有限責任日本誕生学協会 代表理事、へルスカウンセリング学会会員。1997年から妊娠前から産前産後までをサポートするスクールを開講する傍ら、官公省庁の委員や、大学や学会での調査研究にも従事。
行政民間での研修講師、講演、執筆、テレビ番組の出産シーン監修などで活躍中。
21歳大学生から7歳小学1年まで2男3女の母。▼ 誕生学協会(http://www.tanjo.org/)
▼ バースセンス研究所(http://www.birth-sense.com/)著書:「35歳からのおめでたスタンバイ」、「怖くない育児--出産で変わること、変わらないこと 」(講談社文庫)、「いのちってスゴイ!赤ちゃんの誕生--おなかの中のドラマと生きる力」(知の森絵本)、等多数
〈Message〉
5回の出産を経験し、5人の未来人を育てながら、幸せなお産を増やすための仕事も生んできました。生まれてきたこと、生きていくことが辛くなる出来事はいつの時代にもあるけれど、今こそ「自分の誕生におめでとう!」と言いたくなる映画を生み出したい。 観てくださるすべての人たちが、これからの自分から生まれることになっている「ヒト・こと・モノ・出会い」を楽しみに、ワクワクできますように。そしてちゃんと怒ったり泣いたりして、ホッとする、、、、。自分をゆるし、心ゆるむ、本来の子宮のような居心地のよさをクリエイトできたらと思います。

-
見尾保幸
ミオ・ファティリティ・クリニック院長(http://www.mfc.or.jp/)
1949年岡山県生まれ。鳥取大学医学部卒業後、同大学で産婦人科医師として勤務。在籍中、今では必要不可欠となった経膣超音波検査装置の開発に携わる。1993年、ミオ・ファティリティ・クリニックを開院し、本格的に生殖医療に取り組む。1997年、国内では初となる無精子症の妊娠に成功する。現在では、世界で唯一の特殊な装置(シネマトグラフィ)を開発し、ヒトの受精卵の発育研究に取り組み、世界的に注目されている。著書に「心とからだの声を聞こう」(今井出版)等。

-
岡井崇
昭和大学医学部産婦人科主任教授/日本産科婦人科学会常務理事
1947年和歌山県生まれ。東京大学医学部助教授、総合母子保健センター愛育病院副院長などを経て、2000年より昭和大学病院総合周産期母子医療センター長。厚生労働省の「小児科・産科の若手医師の確保と育成に関する研究」の班員として産科医師不足の原因分析にあたり、産科医の過酷な労働条件と、それを敬遠する学生気質ならびに訴訟の多さに注目。一般社会の理解を得ることの難しさを痛感し、小説「ノーフォールト」として出版。2009年10月から藤原紀香主演のドラマ「ギネ産婦人科の女たち」(日本テレビ)の原作となる。ほかに、「壊れゆく医師たち」(岩波ブックレット、2008年、共著)など。

-
吉村正
吉村医院院長(http://www.ubushiro.jp/)
1932年生まれ。医学博士。名古屋大学医学部卒。吉村医院・お産の家院長。自然出産を実践する第一人者。1961年、先代の父に代わって吉村病院院長に就任。以後、45年間に渡って2万例以上の自然なお産にとり組む。産院の裏庭に江戸時代の茅葺き民家を移築し、そこで安産のために、妊婦に薪割りなどの「古典的労働」をすすめている。1999年には、日本の伝統的な様式で「お産の家」を建築、和室で自然なままのお産を行う。現在も現役でお産に立ち会い、外来の妊婦に個別的で丁寧な指導を行っているほか、全国各地で講演会を勢力的にこなしている。著書に「お産!このいのちの神秘―二万例のお産が教えてくれた真実」(春秋社)等。